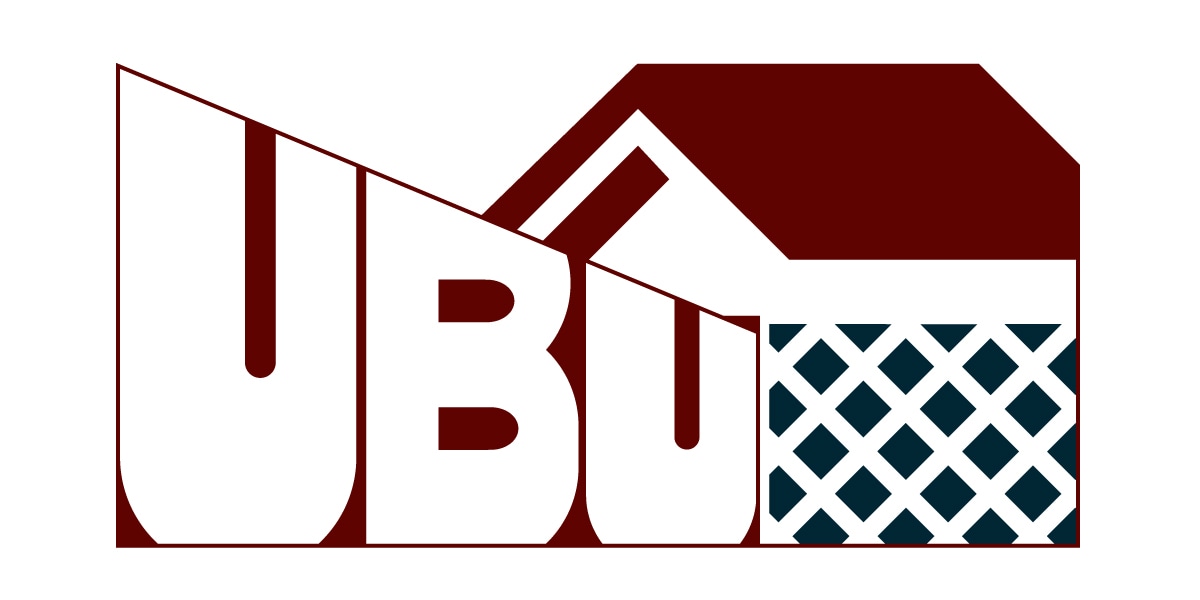2020/05/16 20:20
前回の記事では、「多様性とアファーマティブ・アクション」と題して、なぜアートに多様性が必要なのか、そしてアファーマティブ・アクションとはどのようなものなのかを述べてきました。
今回は、「文化の盗用と権威」と題して、アートにおける差別に迫ってみたいと思います。
「文化の盗用」も、多様性と同じく、最近耳にする機会の増えた単語ですね。
例えば白系のハリウッドスターが、アフリカ系の民族衣装をイメージさせるようなドレスで広告に掲載されたりすると、それは「アフリカ系の文化を白系が盗用している」とされ問題化してしまいます。
このような例では特に、「ホワイト・ウォッシュ」という言葉もあわせて批判に用いられています。
その名の通り、有色人種の文化に類するものを、白系の人種(ホワイト)が大々的に利用することを問題として指す用語で、アフリカ系の例以外にも、アジア系やメキシコ系などの文化を白系人種が転用すると、ホワイトウォッシュ、文化の盗用と言われてしまうようです。
(最近では、とある白系のセレブが「kimono」という名前の下着を発売しようとして、それは日本文化の盗用、ホワイトウォッシュだと批判されていたのが記憶に新しいですね。)
それでは、例えばアメリカの白系女性セレブがイギリスやドイツの服飾・スタイルをまねた場合は、文化の盗用に該当するのでしょうか。もちろん白系対白系なので「ホワイトウォッシュ」には当たらないところですが、文化の盗用として問題化しうるかというと、正直微妙なところでしょう。
つまり文化の盗用が批判的な文脈で用いられる際には、「ホワイトウォッシュ」が重要な要素となっているのです。
この理由を考えてみると、前回の「アファーマティブ・アクション」で論じてきたとおり、歴史的な背景に目を向けざるをえません。
たとえば1960年代、アメリカではアフリカ系の音楽に強い影響を受けた白系の歌手が誕生し、「ブルーアイズソウル」(=青い目の白系のソウルミュージック)と呼ばれるジャンルが確立しました。
しかし、ソウルミュージックはもともとアフリカ系の間で生まれた音楽であり、さらに元をたどれば、祈りの歌であるゴスペル、そして、奴隷として農作業に従事させられていたアフリカ系が農作業で歌ったとされるブルースを起源とする音楽です。
ブルーアイズソウルの音楽的価値を脇に置いて考えると、アフリカ系の人々が白系から受けた差別により生まれた魂の叫びを白系の歌手が歌う、という構図は、とても侮蔑的なものなのではないでしょうか。
このあたりの事情は、かなり脚色されていますが映画の「ドリームガールズ」などでよく表現されているかと思います。
音楽のみならず、同様の現象は多方面で発生していました。
また、アフリカ系に限らず、ネイティブアメリカンも同じ境遇に立たされてきました。
これはもちろん、アフリカ系やネイティブアメリカンの文化が魅力的であり、その文化が人種の垣根を超えたためなのですが、問題は適切なリスペクト、そして対価が払われなかったという点にあります。
このような反省がバックボーンにあるためか、やはり「白系が有色人種を」という一方通行な文脈において文化の盗用という用語は用いられます。
それでは、アフリカ系やネイティブアメリカンに起源を持つ人が、白系セレブの文化・スタイルを用い、何らかのアクションを取った場合、それは批判の対象にならないのでしょうか。
立場が逆であればまさに「ミンストレル・ショー」として大いに批判されるべきでしょうが、アフリカ系が白系を演ずる場合において、それは「パロディ」(=皮肉)として、好意的に解されます。
少し古い例ですが、第71回アカデミー賞(1999年)授賞式では、アフリカ系のウーピー・ゴールドバーグが、白塗りに豪華なドレスを着て、あたかもエリザベス1世かのような挨拶をして笑いを誘いました。
ここではつまり、白系人種が「権威」であり、アフリカ系をはじめとする有色人種が「非権威」であるという構造のもと、権威が非権威をまねることは盗用であり、非権威が権威をまねることはパロディであるという関係性が築かれているのです。
翻って日本では、歴史的に見ても、欧州の「植民地」となったことはありません。
第二次大戦後の戦後処理においてGHQの管理を受けたことはありますが、それ以前に、強国の搾取や奴隷的な隷属を受けたことがないのです。
また経済的にも恵まれており、教育水準も国際的に見て高いため、自らが「非権威」であるという認識を持ちづらく、「文化の盗用」の基本概念を理解しづらいのではないでしょうか。
現に、先にあげた「kimono」下着の事件が話題になった際、日本国内のネット上では「そんなことは気にしない」「差別だというほうが差別だ」などという声が噴出したことを記憶しています。
ただし、これは実害のある可能性を無視した議論です。
下着の発案者は、当然ですが「kimono」という名称をアメリカで商標登録しようとしていたのです。
商標には「カテゴリ」の概念があり、すべての分野において「kimono」という用語が下着をさすことにはなりませんが、少なくとも米国の下着業界内では、「kimono」といえば件の下着そのものを指すことになりかねなかったのです。
これでは、日本国内の着物業界が作り上げてきたブランドイメージに誤解がうまれ、商業的な機会損失につながる可能性も出てしまいます。
「良いものだから用いる」そして結果として「別のものとして消費される」という構造、これはまさに、ソウルミュージックの例と同様の流れです。さらに「本来の着物が締め出される」という可能性まであったのですから、これは気持ちの問題ではなく、商業的な脅威だったわけです。
アートの話で先に進むと、例えばスプレーアート(グラフィティ)などは、ヒップホップやロックの影響のもと産まれ、メキシコや米国ダウンタウンのアフリカ系文化圏の中ではぐくまれたものでした。
そしてこれは表現自体が器物損壊行為であることが多く、アウトローや貧困層の文化と深く結びついたものでもあります。
それが1980年ころから白人文化に取り込まれ、前衛芸術としての地位を築いてゆくこととなります。
ここからは私個人の見解となりますが、そもそもカウンターカルチャー、それもアウトロー的、アナーキスト的な下地の上で昇華されたグラフィティを、裕福な白系が合法的に賞賛されながら行うことに、何の価値があるのでしょうか。
表現されたものの美しさやメッセージ性は理解できる部分もありますが、やはり文化的にみて、グラフィティは違法行為であることがその骨子をなしているのです。
(もちろん、違法行為を称賛しているわけではありません。)
私がグラフィティとは違法行為であることが前提だとしているのは、違法であるからこそ「消去される」またはオープンであるからこそ「上書きされる」という作品の断続性によって、その技術や表現方法が洗練されてきたためです。
そのため、合法的な芸術作品としてのグラフィティには、正直違和感を覚えてしまうのです。
私が違和感を覚えた例としては、2019年に日本国内でみつかった、いくつかのバンクシー作とされるスプレーアートに対する「管理者の態度」でした。
東京都内で発見されたものについては、保護され、看板がたてられ、都知事が記念撮影する、という事態になりましたが…これについて、皆さんはどのように感じられましたでしょうか。
そもそもグラフィティやスプレーアートは、作家・鑑賞者という一対一の関係性ではなく、作家・管理者・鑑賞者という三角関係がついて回ります。
そして元来の意味でのグラフィティにおいて、「管理者」は常に作家を憎悪し、排除するものであったのです。
(リーガル・グラフィティなどの近代のシステムは除きます。)
そして作家も、管理者に代表される社会や資本に対し、憎悪したからこそ文化としてグラフィティが継承されてきたのです。
国内のバンクシーと噂された作品のうち、千葉県印西市の管理者については、とても理想的な反応を示してくれたと個人的には思っています。つまり、「鑑定にも出さず、落書きなので消す」という対応です。
印西市のスプレーアートがバンクシーのものであることはまずないと思いますが、これが仮にバンクシー作のものであったとしても、東京都の対応と比べ、なんと「グラフィティという枠」に沿った対応なのでしょうか。
整理をすると、グラフィティにおいても、「権威」と「非権威」の関係性が重要なのであり、「非権威」であるアウトロー、アナーキストたちが「権威」である公共や資本に対し反逆するからこそ作品が意味を成すのです。また「権威」側も「非権威」の暴虐を憎悪し、抑圧しようとするからこそ、その間に生まれるグラフィティが単なる落書きではなく、文化の火花を上げることができるのです。
このような権威の構造によって生まれる表現は、カウンターカルチャーの系譜を汲むものに共通した基本骨子です。
今一度、自分の表現についてその源流を解剖し、「権威」「非権威」のどちらに自分が属しているのか、そして自分の立場に照らし、文化に恥じない活動ができているのかということを考えてみてください。
日本においても多くの作家が権威と非権威の断絶を認識し、これを埋めようとする、あるいは憎悪する、または無視しようとする…様々な社会的アプローチを含む作品が表現されることを願っております。
※繰り返しになりますが、許可のないグラフィティ・スプレーアートは器物損壊です。管理者に多大な経済的損失を与える行為でもあり、弊社はこのような行動を扇動・賞賛するものではありません。