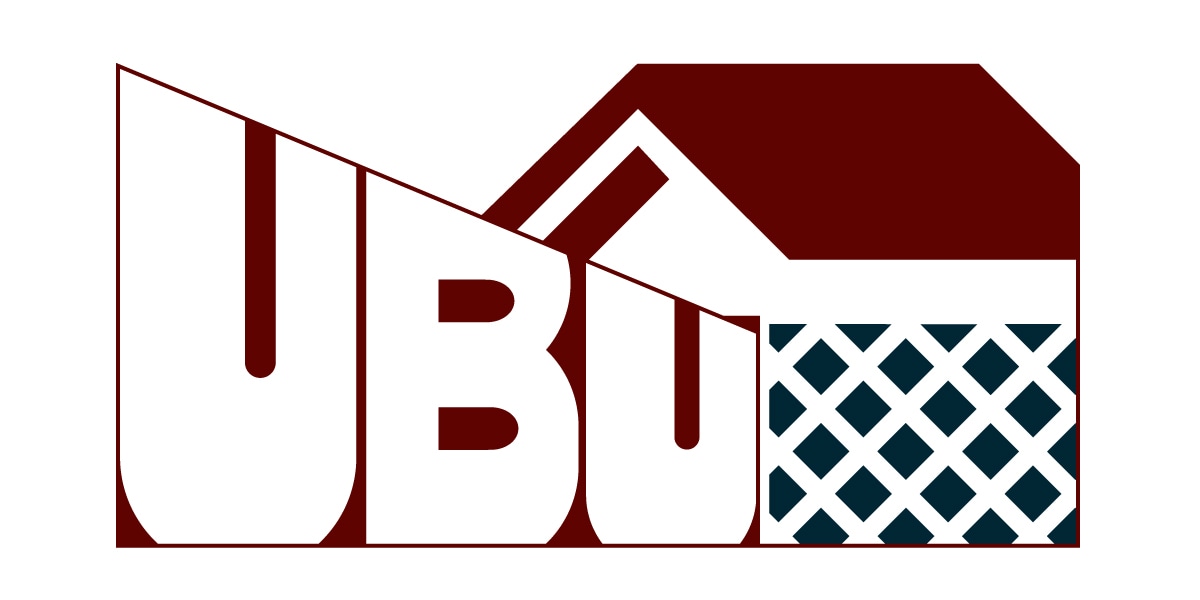2020/06/02 22:54
連続記事として掲載を始めた「アートと差別」ですが、今回で3回目を迎えました。前回の記事(文化の盗用と権威)、前々回の記事(多様性とアファーマティブ・アクション)につづいて、今回は「表現の不自由展とはなんだったのか」をテーマに取り上げたいと思います。
これはアートというよりも「より政治的な」話題なので、ここで取り上げるのは不適切かもしれませんが、アートと差別、という文脈を日本で令和の時代に語る場合、この問題を避けて通ることはできないと思いましたので、筆をとりました。
まず、表現の不自由展に対するアート界隈の反応を整理してみましょう。
どれもリンクを踏むまでもなくお分かりになると思いますが、表現の不自由展はアートの一環なので、それに政治介入・検閲することは横暴であり文化に対する脅威だ、という構成になっています。そしてどれもお決まりの「ヘイトクライムだ」という論調に落ち着きます。
始めに申し上げますと、私個人、そして「UBUartworks」は、このようなアート界隈の論調には賛同しかねます。
特に、権威ある団体や、影響力のあるメディアが若手の美術家などを扇動して、あたかも「アートの総意である」として文部科学省や政権の批判を行うことには、ここに抗議させていただきたいと思います。
それでは、なぜ私たちが表現の不自由展をめぐる騒動について、既存のアート界隈とは真逆の態度をとるのか、「アートと差別」という文脈で説明したいと思います。
(歴史修正的な意見ではありませんので、そのような内容を期待されている場合はご容赦ください。)
まずは表現の不自由展の概要を整理してみます。
2005年に愛知県で行われた「あいち万博」の理念と財産を引き継ぎ、2010年から3年ごとに行われている国際美術展覧会(トリエンナーレ)が「あいちトリエンナーレ」です。そして、その4回目にあたる2019年(テーマ:情の時代)の一部での展示が「表現の不自由展」と題したものでした。
展示のコンセプトは、公立美術館で撤去された(=表現の自由の枠外にこぼれてしまった)ものを拾い集めて一堂に会する、というもので、それゆえ、過激なものが多いことが特徴でした。
展示内容で特に話題となったものは従軍慰安婦や憲法9条、昭和天皇、戦争などをテーマにしたものでしたが、それ以外にも原発や人種差別をテーマにしたものもありました。
ここまでが前提の整理です。
後日騒動の中心になる愛知県知事や芸術監督の政治姿勢を論ずることはしませんが、展示のテーマや方法だけをみると、非常に興味深い、むしろ「Socially Engaged Art」的な文脈からすると理想的な取り組みだということができます。
ただ作品の中には、戦死した日本兵や昭和天皇に対し侮辱的ともとれる表現があり、大きな反対運動が巻き起こりました。
そして暴力的かつ先鋭的な意見が大きくクローズアップされ、批判と擁護の応報はヒートアップし、ついには実行委員会への脅迫行為までがなされるようになり、社会問題になったのです。
ここでしきりに取りざたされたのが「ヘイトクライム」という語でした。
表現の不自由展に反対する者は「日本や天皇に対するヘイトだ」といい、賛同する者は「反対することこそヘイトだ」と応報しました。
ヘイトクライムの定義には、少数に対する弾圧、という前提が付きますので、「大多数」であるものに対するヘイトは成立しません。さらに国内の「ヘイトスピーチ解消法」には、ヘイト成立には「本邦外」(=日本国外)の人に対するものでなければならないと明記されていますので、いずれにしろ「日本や天皇に対するヘイト」という言葉は成立しません。
それでは表現の不自由展に反対することがヘイト、差別になるのかというと、それにも同意することができません。
ここで注目すべきは、歴史的な事実や会場の利用規則、補助金の交付細則などではなく、「どのような意図で企画をし、その結果どのようになったのか」です。
メディアやアート界隈はこの問題を「無教養な右翼vsアートを理解するリベラル」、または「弱い文化vs強い国家」という単純化した二項対立問題として表現してきました。
しかし、実際は構造を単純化すると「リスクを前提とした展示⇒リスクを軽視した委員会⇒問題として顕現したリスク」というものになります。つまり、表現の不自由展ははじめから社会的に議論を招くことを前提としたアート作品なのだから、噴き出したエネルギーや反応を展示にフィードバックする素地を整えておく必要があった、ということです。
文化とは強大な力を秘めたエネルギーの塊です。
そしてそのエネルギーが噴出したとき、アートや宗教、哲学などの形を伴って結晶するのです。
かつてルドヴィーゴ・スフォルツァがダヴィンチを召し抱え築城し、コンスタンティノープルがイスラムに陥落し、北一輝をよりどころに青年将校がクーデターを起こしたように、文化は時として国家を破壊しうる力を持ちます。
特に「差別」、異なる文化や価値観同士がぶつかり合うことで生まれるエネルギーの強大さといびつさは、少し歴史を振り返るだけで容易に理解することができます。
私は表現の不自由展において、この力を見くびり、自分たちにコントロールできると考えていた運営側にこそ、重大な落ち度があると考えています。
観方を変えてみると、「あいちトリエンナーレ」は「ヴェネツィア・ビエンナーレ」とほぼ同規模の強大な権威をもったものであり、またその委員長は愛知県知事という体制側の存在です。
はっきりいって、この体制側、権威側が表現の不自由展で取り上げた問題(=差別)を過少に評価し、些末なものだと扱ってきたのではないでしょうか。
例えば会場において、内容に賛成するものと反対するもののインタラクティブな場を用意する。一部の作品については破壊されることを前提(許可)とする。即興で自由な意見を表現できるスペースや素材を用意する…などなど、この企画のエネルギーを適切に発散させる方法はいくらでもあり、事前に趣旨を丁寧に説明する機会を設けることもできたはずです。
受け皿を用意せずに炎上しそうなものを企画するのは、キュレーションではありません。
くわえて残念なことは、「その後」に起きた様々な問題です。
批判の声の一部が、やがて脅迫や恫喝に代わり、ついに「安全性の面から」展示が一時中止となってしまいました。
そしてそれから様々なゴタゴタがあり…最終的に、政治と見栄が均衡を保ち、なんの工夫もないまま、展示は再開されてしまいました。
展示趣旨についての世間の理解が深まらず話題性ばかりが先攻し、また適切な受け皿の用意、展示方法の工夫をする間もなく、ただ再開されたのです。
この際、メディアの規制や来場者に対してSNS投稿の禁止を求めたので、そもそもの趣旨さえもいびつになってしまい、どこに対しても、ただただ「炎上した」だけの展示となってしまいました。
さて、このような一連の騒動は政治問題にもなり、「検証委員会」が設けられることとなりました。
検証委員会は様々なアプローチをしたようですが、最終的に「反知性主義」という言葉にすべてを押し込んでしまいました。
一昔前の権威主義者たちがよく使った言葉で非常に頭が痛いところですが…
ちなみにWikipediaの「反知性主義」内、「日本における反知性主義の用法」の項目に興味深い記述があるので以下に引用します。
==========================================================================================================
日本においては、2015年に論壇などで多用され、一種の流行語となったが、単に知性の無い者として批判する際に用いられることが多い。冷泉彰彦は、この語が使われる局面は「『イデオロギー上の論敵の中にある感情論に対して敵意を持つ』ことであり、それ以上でも以下でもない」「その敵意自体も相当程度に感情論であることが多い」と指摘している。
==========================================================================================================
キュレーションの能力やリスクマネジメントに踏み込まなかったので最終報告書には非常にがっかりしました。
(たしか中間報告では触れていたと思うのですが)
結果として、「差別」を扱うことで社会的な暴力性を顕在させ、さらに「差別」の溝を深めてしまったのですから、どう考えてもこの展示の趣旨からして失敗です。
また、この失敗に目を向けず、社会調査的な手法を無視した単純なアンケートと有識者へのインタビューのみで問題の矮小化をはかった検証委員会の結論も、問題の本質や今後のあるべき姿を明示するものではありませんでした。
知事はトリエンナーレ終了後「違う立場や意見を認めず、徹底的に攻撃することがまかり通る日本の社会に驚きを感じた」と述べているようですが、驚きを感じている場合ではありません。そのような認識で差別を取り上げ、問題を放置したことにこそ驚きを感じます。
さらにこれは別の問題ですが…
表現の不自由展が相次ぐ脅迫により、展示中止に追い込まれてしまった際、日本ペンクラブや公益社団法人日本漫画家協会もこれに対し「憂慮」などの声明を発表しています。
もちろん暴力や脅迫に屈して表現が捻じ曲げられてしまうことは重大な危機ですが、「漫画村」や「Anitube」などの海賊版サイトへの接続を「民間業者が自主的に接続できないようにする」(=ブロッキングする)よう国が緊急に対策を行ったことについて、これらの「知る権利」や「表現の自由」を重視する団体がどのように考えているのかはぜひ聞いてみたいところです。
特定者の収益を保護するため、法律に基づかずに国民全体の情報統制を国が主導し行っているのですから、これはかなり重大な検閲です。
さらに、「国が特定の情報へのアクセスを禁止できる」という全体主義的な悪しき前例なのですから、当然「知る権利」を守るために、出版に携わる方々には戦っていただきたいと思います。
話がそれました。
政治的なもの、権利についてをアートの文脈で扱い活動を行う際、かならず「うねり」が発生します。
それが人の情に深く分け入るものであれば当然ですし、それが狙いのはずです。
その結果怒り狂う人がいたとして、「反知性的で驚いた」というのではただの悪趣味な社会風刺にすぎません。
より社会にインパクトを持つ、つまり社会の構造を変革したり、見る者の意識を変えるようなアートを目指すのであれば、衝撃的であることとあわせて、その衝撃に対する「反響」をどのように扱うのか、吸収するのかを考えてみるべきです。
これ以上表現の不自由展のようなものが増え、今以上に日本国内でのアートと社会性の融合が変質・誤解されてしまう前に、アート界隈は象牙の塔から反知性主義者とレッテルした者を見下すのではなく、「想像力」をもって活動にあたってほしいと願っています。